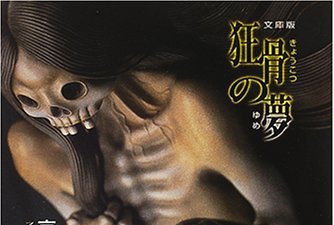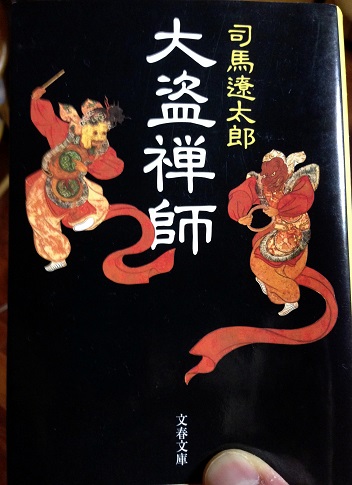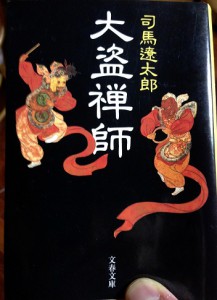日々読書に励んでいるつもりだが、10月は再読の月としたいと思う。
最近再読して良かったのが、京極夏彦の「狂骨の夢」。

一冊一冊のブ厚さが常に話題の京極夏彦《百鬼夜行シリーズ》の3冊目。
先日、17年ぶりのシリーズ最新巻「鵼の碑(ぬえのいしぶみ)」が出て。
復習のため百鬼夜行シリーズを読み返してきたのだが、初読の時はピンとこなかった「狂骨の夢」が大変おもしろかった。

トリックがわからない状況で読むと、わけがわからなすぎて読んでいて気持ち悪い程なのだが、再読して巧妙に話をまとめて書かれているのがわかった。
すごい小説だったのだなぁ、と気付くことができた。

むずかしい本ほど再読しないといけないし、1回の読書で全てわかるような本ばかり読んでいてもだめなのかなと思う所もある。
再読は本の内容をより深く読みこめるのは言うまでもないとして、もう一つ効能がある。
単純に読むのが早くなるということ。
再読する価値があると思う本なら、自分の中では面白かったんだろうし。
面白い本は読むのが早い。
「この本、本当に読む価値があるのかなぁ〜?」
なんて疑っているとなかなか読み進まない。
先述した「鵼の碑」も、半分まで読むのに1週間かかったが、残り半分は3日で読めた。
やはり、おもしろくなってからが読書は加速する。
読書量を増やせるのは良い。
もっとも、本を読むのは冊数のためではなく、自分の頭の中につめこんだものが、どう働くかが全てである。
そう「すべてがFになる」で有名な森博嗣が、「読書の価値」で言っていた。(という覚えがある)
確認のため、「読書の価値」も読まないとだな。