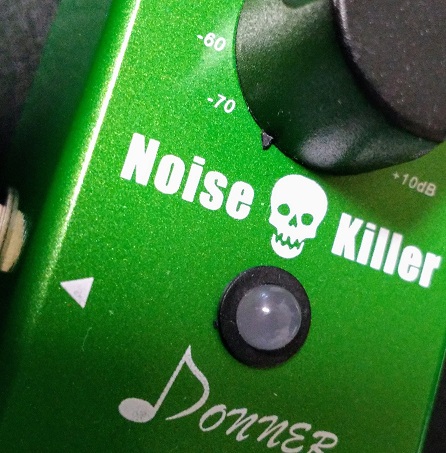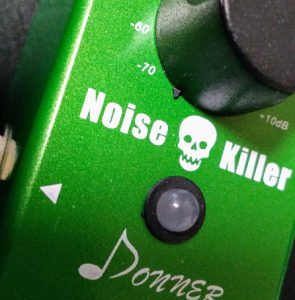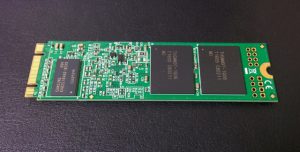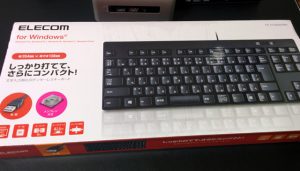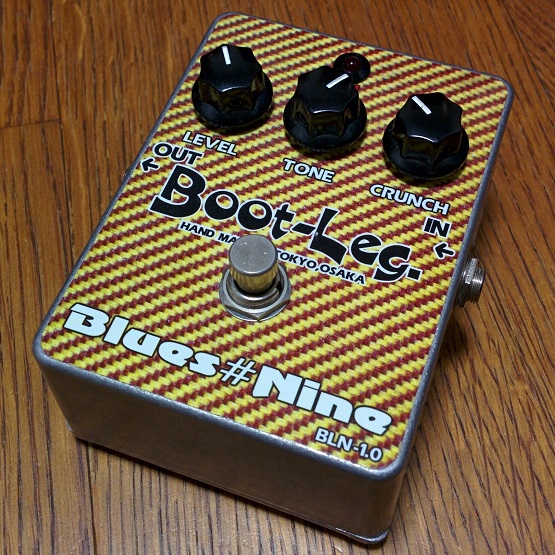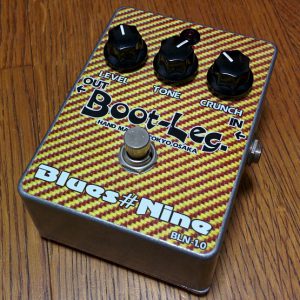エフェクトボード重いです!
毎回スタジオ練習に持っていくの辛いです!
という訳で軽装ボードを組みました!
構成は以下の通り。
ギター→BOSS FV-50L (ボリュームペダル)
→T-REX VULTURE (ディストーション)
→Donner Noise Killer (ノイズゲート)
→Bheringer VD-400 Vintage Delay (アナログディレイ)
→JC-120 (スタジオアンプ)
画像上段の赤いのはチューナーKORG PitchBlack Portable。
ボリュームペダルのチューナーアウトに接続。
それぞれ見ていきましょう。
BOSS FV-50L

Bossの定番ボリュームペダルです。
エクスプレッションペダルの割に軽量。
難点はギアが悪いのかポッドが悪いのか、イマイチ踏んだ感覚で効いてくれない所かな。
ミニマムボリュームが設定できて音量調節にはもってこいのはずなんだけど。
「ちょっとギターうるさいかなぁ」と思った時に気持ち音を絞ります。
T-REX VULTURE
デンマークの老舗、T-REX製ディストーション。
値段は高いが性能は折り紙つきという印象のメーカーですね。
実勢価格15,000円オーバーの所をヤフオクで5,000円ぐらいで落札できました!
元々の値段の割に軽量。
安ディストーションにありがちな、ワザとらしい歪み感が無くて良い。
サウンド的にはカラっといった感もなく、重低音という感もなく。
バランス型ってところでしょうか。
EMG85ピックアップとの組み合わせはイイカンジ。
歪みエフェクターで一般的な3コントロールに加えて、LowBoostとFat(ミドル?)Boostを搭載。
ジャズコーラスで鳴らす場合はLowBoostをかけて低音域を支える。
FatBoostは基本カット。
「ワウ半止め音」にするツマミのようで、モコっとなるので。
落札した当時は後段にオーバードライブをつないでゲインアップして使用してましたが、MXR5150オーバードライブを購入した為お役御免に。
この度めでたく復帰。
Donner Noise Killer

先日紹介したDonnerの格安ノイズゲートです。
大きさと相まって軽量。
T-REX VULTUREのノイズ対策として導入しました。
実はVULTUREノイズ多い。
ツマミの位置で効きがシビアに変わるので、テープ等でツマミを固定する必要があるかも。
[blogcard url=”http://stajivan.com/archives/2679”]
Bheringer VD-400
[blogcard url=”http://stajivan.com/archives/2594”]
みんな大好き、ベリンガーの格安アナログディレイ。
ステレオでキルドライとか面倒なことはせず、直列に接続。
気持ち長めのショートディレイを4回ぐらいフィードバックさせて、
いわゆる「スラップバック・ディレイ」として使用しました。
アナログディレイ特有のあたたか味というかレトロ感も相まって、
コーラス等モジュレーションが無いのを補足するねらいもアリ。
本体を含めてスイッチ部もプラスチック。
配慮して優しく踏むとセンサー感度悪い。
しっかり踏まないとダメだけど、耐久性に不安が残るというジレンマ。
軽量で良いんだけど。
発振サウンドもなかなか良いので飛び道具にもヨシ。
KORG PitchBlack Portable
KORGの定番ペダルチューナー、”PitchBlack”の横長版。
配電機能があるので、パワーサプライ替わりに。
ケーブルチェッカーもついているので、セッションなどの実戦には重宝するのでは。
“Portable”と名乗る割にデカくて重い。
その分、安定して設置できる。
表示もデカくて、ひたすら見やすい。
ペダル型全盛のチューナー界において横長型としては最高峰なんじゃないかな、本器は。
しかし生産終了済。
売れなかったのかなぁ。
トゥルーバイパス未対応なのと、本器のバッファーがあまり音良くないのが原因かな。(個人の感想です)
まとめ
音色としては「歪みとディレイ」という、必要最低限よりちょっと足りてない構成のボードですが。
そこそこ普段の音は再現できてるらしいです。
やっぱりギタリストの技量がサウンドを作るんですな!
ははは。
エフェクター少ない構成のボードにも、それはそれで生まれる表現力があるので、普段でっかいボード持ち歩いてるのはうーん、どうなんでしょうーって思ってしまうところがエフェクター沼に沈んでる証拠でしょうかそうですか。